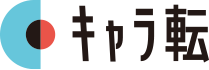キャラクターをどこまで利用できる?著作権の保護と侵害について解説
SNSでの発信や二次創作、オリジナルグッズの制作など、キャラクターを活用する機会が広がっています。しかし、その利用には著作権や商標権といった法律の壁があることを理解しておく必要があります。
本記事では、「キャラクターはどこまで利用できるのか?」という疑問に答えながら、著作権の基本、侵害リスク、ビジネス活用時の注意点などをわかりやすく解説します。
本記事では、「キャラクターはどこまで利用できるのか?」という疑問に答えながら、著作権の基本、侵害リスク、ビジネス活用時の注意点などをわかりやすく解説します。
キャラクターをどこまで利用できる?
キャラクターの利用には明確なルールがあるため、無断利用は原則として認められていません。厳密にいうと、キャラクターそのものには著作権というものはありません。著作権が付与される要件の一つに「表現されたものであること」が含まれており、キャラクターそのものはこれに該当しないことから、著作権の保護対象とはなっていません。
ただし、キャラクターを漫画やアニメ、イラストなどで具体的に表現することは、この「表現されたものであること」という条件を満たすこととなるため、著作権が発生します。
実際に、ポパイの漫画の図柄をネクタイに使用したことが争点となった裁判では、ポパイというキャラクターそのものに対する著作権は認められなかったものの、ポパイの登場する漫画の著作権が認められ、ネクタイは著作権侵害と判断されました。なお、一定の条件下での「引用」や「パロディ」、著作権保護が切れた作品の利用など、例外も存在します。ここでは、キャラクター利用に関する法的な側面について詳しく見ていきましょう。
著作権の保護期間は、著作者の死後70年とされています。法人が著作権者である場合は、公表後70年が一般的です。つまり、昔のアニメやゲームキャラクターでも、著作権が残っているケースは多く、自由に使えるとは限りません。
また、民事上の損害賠償請求を受けるリスクもあり、個人でも訴えられるケースがあります。著作物に似ているからといって必ず侵害になるわけではありませんが、「依拠性(元作品を参考にした)」と「類似性」が認められると、侵害と判断される可能性があるため注意が必要です。
また、キャラクターの造形や装飾などがデザインとして保護されている場合は意匠権の対象となることもあります。著作権の保護期間が終了しても、商標や意匠権は存続している可能性があるため、利用前に確認が必須です。
著作権に関するより詳しい解説は、こちらの記事をご覧ください。
≫キャラクターIPとは?活用のメリット・デメリット・事例や関連職種も紹介!
ただし、キャラクターを漫画やアニメ、イラストなどで具体的に表現することは、この「表現されたものであること」という条件を満たすこととなるため、著作権が発生します。
実際に、ポパイの漫画の図柄をネクタイに使用したことが争点となった裁判では、ポパイというキャラクターそのものに対する著作権は認められなかったものの、ポパイの登場する漫画の著作権が認められ、ネクタイは著作権侵害と判断されました。なお、一定の条件下での「引用」や「パロディ」、著作権保護が切れた作品の利用など、例外も存在します。ここでは、キャラクター利用に関する法的な側面について詳しく見ていきましょう。
著作権で保護される対象と期間
キャラクターが著作権で保護されるかどうかは、その創作性と表現の独自性に左右されます。たとえば、単なる名前やシンプルな図形では保護されないこともありますが、ストーリー性を持ち、視覚的にも独自性の高いキャラクターは著作物と認められる可能性が高いです。著作権の保護期間は、著作者の死後70年とされています。法人が著作権者である場合は、公表後70年が一般的です。つまり、昔のアニメやゲームキャラクターでも、著作権が残っているケースは多く、自由に使えるとは限りません。
著作権を侵害する行為と罰則
著作権を侵害する主な行為には、無断転載や商用利用、改変や二次配布などが挙げられます。たとえば、人気キャラクターのイラストを自身のグッズに印刷して販売する行為や、ファンアートを無断で公開・収益化する行為は、著作権侵害に該当する可能性があります。著作権侵害には厳しい罰則があり、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、もしくはその両方が科されることもあります。また、民事上の損害賠償請求を受けるリスクもあり、個人でも訴えられるケースがあります。著作物に似ているからといって必ず侵害になるわけではありませんが、「依拠性(元作品を参考にした)」と「類似性」が認められると、侵害と判断される可能性があるため注意が必要です。
キャラクターの商標権・意匠権
著作権とは別に、キャラクターには商標権や意匠権が設定されていることもあります。たとえば、ロゴやキャラクターを企業が商標登録している場合、それを無断で使用すると商標権侵害になることがあります。また、キャラクターの造形や装飾などがデザインとして保護されている場合は意匠権の対象となることもあります。著作権の保護期間が終了しても、商標や意匠権は存続している可能性があるため、利用前に確認が必須です。
著作権に関するより詳しい解説は、こちらの記事をご覧ください。
≫キャラクターIPとは?活用のメリット・デメリット・事例や関連職種も紹介!
キャラクタービジネスにおける著作権の注意点
キャラクターを活用したビジネスでは、権利の取り扱いを誤ると、法的トラブルに発展する可能性があります。ここでは、著作権に関する実務上の注意点を見ていきましょう。
このような事態を防ぐためには、制作前または納品時に、著作権の譲渡契約を結ぶことが重要です。契約書には、著作権が誰に帰属するのか、どの範囲まで使用できるのか、二次利用は可能かなどを明記しておく必要があります。また、キャラクターに複数の制作者が関係している場合、それぞれの貢献度や権利の割合も明確にしておくことで、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。
● 他社キャラクターとデザインや名称が似ているか不安なとき
● 海外展開を検討しており、国際的な権利問題が懸念されるとき
● 外部クリエイターと共同制作を行うとき
● 他社とのコラボ商品をリリースするとき
弁護士や弁理士、知的財産に詳しいコンサルタントなどの専門家に相談することで、万が一の訴訟や損害賠償リスクを回避できます。法的トラブルは、発生してからの対応では費用も時間もかかるため、事前の予防が重要です。
ライセンス契約に関する詳細は、こちらの記事をご覧ください。
≫キャラクターライセンスとは?契約の注意点やライセンスビジネスの求人も紹介
権利の帰属と譲渡
キャラクターを開発する際、まず整理しておくべきなのが「著作権の帰属先」です。キャラクターを社内で制作したとしても、その著作権が自動的に会社に帰属するとは限りません。たとえば、外部のイラストレーターやデザイン会社に制作を依頼した場合、著作権は原則としてその制作者に帰属します。たとえ報酬を支払っても、契約上で「著作権の譲渡」や「使用許諾」に関する取り決めがなければ、企業はそのキャラクターを自由に活用できないことになります。このような事態を防ぐためには、制作前または納品時に、著作権の譲渡契約を結ぶことが重要です。契約書には、著作権が誰に帰属するのか、どの範囲まで使用できるのか、二次利用は可能かなどを明記しておく必要があります。また、キャラクターに複数の制作者が関係している場合、それぞれの貢献度や権利の割合も明確にしておくことで、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。
専門家への相談
キャラクターに関する知的財産は、著作権だけでなく、商標権や意匠権、場合によっては不正競争防止法など、複数の法律が関係してくる複雑な領域です。特に以下のようなケースでは、法律の専門家に早めに相談することが望ましいです。● 他社キャラクターとデザインや名称が似ているか不安なとき
● 海外展開を検討しており、国際的な権利問題が懸念されるとき
● 外部クリエイターと共同制作を行うとき
● 他社とのコラボ商品をリリースするとき
弁護士や弁理士、知的財産に詳しいコンサルタントなどの専門家に相談することで、万が一の訴訟や損害賠償リスクを回避できます。法的トラブルは、発生してからの対応では費用も時間もかかるため、事前の予防が重要です。
ライセンスの契約
既存のキャラクターを合法的に使用するには、著作権者とのライセンス契約が必要です。この契約では、使用目的、範囲、期間、対価などを明記します。たとえば、コラボ商品の展開や広告素材への使用などは、契約書によって細かく規定されるのが一般的です。無断利用が発覚してから慌てるのではなく、ライセンス契約を事前に交わすことで、安心してキャラクターを活用することができます。ライセンス契約に関する詳細は、こちらの記事をご覧ください。
≫キャラクターライセンスとは?契約の注意点やライセンスビジネスの求人も紹介
社内教育
キャラクタービジネスを扱う企業では、社員が著作権に関する最低限の知識を持つことが不可欠です。「知らなかった」という理由は免責にはなりません。社内研修やガイドラインを通じて、著作権侵害を未然に防ぐ教育体制を整えることが求められます。特にマーケティングやデザイン部門など、キャラクターに関わる部署では、実例を交えた著作権教育を定期的に実施することが重要です。キャラクターライセンスの関連職種
キャラクターライセンスに関する仕事には、さまざまな専門職があります。たとえば、ライセンス契約を管理する「キャラクターライセンス担当」や、知的財産を管理する「法務・知財部門」、商品展開を担う「企画・制作職」などが挙げられます。いずれもキャラクターの権利を適切に管理・運用する上で重要な役割を担っており、今後も需要の高まる分野です。
関連職種について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
≫ライセンス業務とは?志望動機や資格・求人・転職について解説
関連職種について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
≫ライセンス業務とは?志望動機や資格・求人・転職について解説
著作権について理解したうえでキャラクター活用を行おう!
本記事ではキャラクターに関する著作権の取り扱いや、利用時の注意点などについて詳しく解説しました。キャラクターの利用には、著作権や商標権、意匠権といった複数の知的財産権が関係しています。十分な知識がないまま必要な確認を行わずに使用すると、法的リスクを招くおそれがあります。一方、正しく理解して活用することで、マーケティングにおいて強力な武器になる可能性も秘めています。
契約や社内教育、必要に応じた専門家への相談など、リスク管理を徹底し、安心してキャラクター活用を行いましょう。また、キャラクター関連のビジネスに携わりたい場合には、ライセンスに関する法的な支援を行う法務関連職種や、商品企画・製作などさまざまな職種が存在します。
日本唯一のキャラクター業界限定の求人サイト「キャラ転」では、さまざまなキャラクター業界関連の職種が掲載されています。キャラクター業界への転職に興味がある方は、ぜひ一度求人情報をご確認ください。
契約や社内教育、必要に応じた専門家への相談など、リスク管理を徹底し、安心してキャラクター活用を行いましょう。また、キャラクター関連のビジネスに携わりたい場合には、ライセンスに関する法的な支援を行う法務関連職種や、商品企画・製作などさまざまな職種が存在します。
日本唯一のキャラクター業界限定の求人サイト「キャラ転」では、さまざまなキャラクター業界関連の職種が掲載されています。キャラクター業界への転職に興味がある方は、ぜひ一度求人情報をご確認ください。
新着の記事
- 3DCGデザイナーのポートフォリオ作成のコツや注意点について
- キャラクターデザイナーに求められるスキルとは?実務で評価される能力を解説
- キャラクターイラストの描き方ガイド|初心者が上達するためのコツ
- 声優が実践したい喉のケア方法!おすすめの習慣やNG行動とは
- 声優は独学でなれる?独学で身につく力・練習法・スクールとの違いは
- コンポジターとは?仕事内容・平均年収とキャリアの始め方を紹介
- ゲームイラストレーターになるには?必要スキル・未経験からの目指し方
- モーションキャプチャーソフトとは?種類や選び方、おすすめの製品について
- キャラクターの性格の作り方とは?魅力を引き出す設定方法を解説
- 造形師と原型師の違いは?仕事内容や求められるスキルを徹底比較