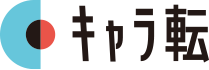企業公式キャラクターのSNSアカウントとは?成功事例や著作権などの注意点を紹介
「自社キャラクターをもっと活躍させたいが、どのSNSから着手すべきか分からない」そんな広報・マーケ担当者は少なくありません。
本記事では企業公式キャラクターのSNSアカウントの概要や運用のメリット・デメリット、注意点などについて詳しく解説しています。また、企業公式SNSキャラクターのSNS運用の成功事例や関連職種についても記事の後半でご紹介しています。
本記事では企業公式キャラクターのSNSアカウントの概要や運用のメリット・デメリット、注意点などについて詳しく解説しています。また、企業公式SNSキャラクターのSNS運用の成功事例や関連職種についても記事の後半でご紹介しています。
目次
企業公式キャラクターのSNSアカウントとは?
企業公式キャラクターのSNSアカウントとは、企業が自社のキャラクターを「中の人」として擬人化し、SNSを活用してユーザーとのコミュニケーションや情報発信を行うアカウントのことです。主にキャラクター自体の周知やブランディング、ブランドや商品の周知などが目的となっています。このようなアカウントの運用では、あたかもキャラクター本人が投稿や返信をしているような形式でコンテンツが発信されるため、ユーザーは親しみを感じやすく、企業への関心や好意を高めるきっかけになります。
企業公式のSNSアカウントでは、どうしてもフォーマルで面白味のない内容になりがちですが、キャラクターに人格を与えることで、より親近感のあるユニークな投稿が可能になります。ユーザーの目に留まりやすくなるなど、多くのメリットがあり、多くの企業で採用されています。
さらに、ユーザーとの双方向のやり取りが可能なSNSでは、コメントや引用リポストなどを通じて自然な形で話題が広がるため、広告に頼らずとも高い拡散効果が期待できます。とくに若年層やSNSに慣れ親しんだユーザー層には、キャラクターが身近な存在として受け入れられやすい傾向があります。
また、キャラクターが時事ネタやトレンドを取り入れた投稿を行う際には、表現に細心の注意を払う必要があります。誤解を招く発言をしてしまうと、企業全体への批判に発展する恐れもあるため、投稿前のチェック体制は必須でしょう。さらに、キャラクターの投稿内容を定期的に考え続ける必要があるため、運用担当者には高い創造力と継続力が求められる点も負担となる可能性があります。
また、キャラクターの発言や表現が一貫性を持つよう、キャラクター設定や行動ルールを「ガイドライン」として文書化することも有効です。こうすることで、複数人での運用や担当者交代があった場合でも、キャラクターのイメージを保つことができます。
なお、キャラクター制作に関する具体的な注意点については、こちらの記事でも詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
≫企業キャラクターとは?人気・有名な成功例・作り方・デザインなど
キャラクターの活躍が直接、企業のブランディングに貢献し、企業を象徴する存在へと成長をしていく様子は何にも代えがたいやりがいや充実感につながるでしょう。また、広報やマーケティングの領域にも関わるため、キャリアの幅を広げたい転職希望者にとっても大変魅力的なポジションです。SNSに強い人材へのニーズは年々高まっており、今後も活躍の場が広がる分野だといえるでしょう。
企業公式のSNSアカウントでは、どうしてもフォーマルで面白味のない内容になりがちですが、キャラクターに人格を与えることで、より親近感のあるユニークな投稿が可能になります。ユーザーの目に留まりやすくなるなど、多くのメリットがあり、多くの企業で採用されています。
運用するメリット
企業公式キャラクターのSNSアカウントを運用する最大のメリットは、キャラクターを通じたストーリー性やインパクトが大きいことから、好感度が高まりやすくブランディングしやすい点です。キャラクターを通して発信することで、企業の堅苦しさを和らげ、ユーザーにとって「話しかけやすい」「応援したくなる」存在に変わります。また、キャラクターの個性を活かすことで、商品・サービスの認知拡大だけでなく、ブランドのファンを獲得することにも繋がります。さらに、ユーザーとの双方向のやり取りが可能なSNSでは、コメントや引用リポストなどを通じて自然な形で話題が広がるため、広告に頼らずとも高い拡散効果が期待できます。とくに若年層やSNSに慣れ親しんだユーザー層には、キャラクターが身近な存在として受け入れられやすい傾向があります。
運用するデメリット
一方で運用するデメリットとして、キャラクターの人格や口調が一貫していない場合、ブランドイメージに悪影響を与えるリスクがあります。担当者が変わったり、投稿方針にぶれが生じたりすると、ユーザーが違和感を抱き、フォローを外してしまうことも少なくありません。また、キャラクターが時事ネタやトレンドを取り入れた投稿を行う際には、表現に細心の注意を払う必要があります。誤解を招く発言をしてしまうと、企業全体への批判に発展する恐れもあるため、投稿前のチェック体制は必須でしょう。さらに、キャラクターの投稿内容を定期的に考え続ける必要があるため、運用担当者には高い創造力と継続力が求められる点も負担となる可能性があります。
運用する際の注意点(キャラクターデザインや著作権など)
企業公式キャラクターのSNS運用においては、キャラクターデザインや著作権に関するルールを明確にすることが非常に重要です。自社で制作したキャラクターであっても、誰が著作権を保有しているのか、商用利用の範囲はどうなっているのかといった点を事前に整理しておかなければ、後のトラブルに繋がるおそれがあります。また、キャラクターの発言や表現が一貫性を持つよう、キャラクター設定や行動ルールを「ガイドライン」として文書化することも有効です。こうすることで、複数人での運用や担当者交代があった場合でも、キャラクターのイメージを保つことができます。
なお、キャラクター制作に関する具体的な注意点については、こちらの記事でも詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
≫企業キャラクターとは?人気・有名な成功例・作り方・デザインなど
業務の魅力
企業キャラクターのSNSアカウント運用を担当する仕事には、企画・発信・分析といった一連のクリエイティブな業務を一貫して経験できる魅力があります。特に自分が生み出したキャラクターや投稿が多くのユーザーに届き、反応をもらえるという実感は、大きなやりがいとなります。キャラクターの活躍が直接、企業のブランディングに貢献し、企業を象徴する存在へと成長をしていく様子は何にも代えがたいやりがいや充実感につながるでしょう。また、広報やマーケティングの領域にも関わるため、キャリアの幅を広げたい転職希望者にとっても大変魅力的なポジションです。SNSに強い人材へのニーズは年々高まっており、今後も活躍の場が広がる分野だといえるでしょう。
企業公式キャラクターSNSアカウントの成功事例
企業公式キャラクターがSNSで注目されるようになった背景には、「顔の見える企業」へのニーズの高まりがあります。企業が公式キャラクターを通じて情報を発信することで、商品やサービスだけでなく、企業文化や理念まで伝えやすくなります。
ここでは、主要なSNSごとに、キャラクター運用がどのように行われているか、実際の事例を交えながら紹介していきます。
Pontaでは公式キャラクターのポンタが週に2回程度、ポンタの日常生活を紹介しており、ポンタのイラストツイートは他のツイートに比べてリポストやリプライも多くなっており、うまくエンゲージメントにつなげている例といえるでしょう。このようにキャラクター性を持たせた投稿スタイルは、ユーザーとの心理的な距離を縮める上で非常に効果的です。
Instagram
Instagramでは、ビジュアル表現が中心となるため、キャラクターのデザインや世界観を魅力的に伝えることが重要です。世界中にキウイフルーツを輸出、販売しているゼスプリでは、キウイブラザーズというキャラクターを活用して、インスタグラムを運用。キウイを使った料理やスイーツの写真には、周りになじむようにキウイブラザーズのぬいぐるみが写されており、自然とゼスプリのキャラクターとして印象付け、エンゲージメントへとつなげています。
また、株式会社ギンビスでは、代表的な商品であるたべっ子どうぶつの着ぐるみを使った写真を投稿しています。
Facebook
Facebookは他のSNSに比べて、ユーザーの年齢層が高く、信頼性や情報の深さを重視した運用が求められます。そのため、キャラクターによるコミカルな発信よりも、社員紹介や社内イベントレポートなどにキャラクターを登場させる手法が見られます。
企業の雰囲気を伝えつつ、ユーザーの関心を引くきっかけとなるため、採用活動やブランディングとの親和性が高いのが特徴です。真面目な印象の中にもキャラクターによる温かみを感じさせる投稿が、好感を持たれる傾向にあります。
TikTokのユーザーは若年層が多く、エンタメ要素の強い投稿が受け入れられやすいため、キャラクターの“遊び心”を活かした戦略が求められます。人間味とバーチャル感のバランスを保ちながら、企業の認知を高められることが大きな強みです。
実写とアニメーションのハイブリッド構成や、ナレーション付きのミニドラマ仕立てなど、表現の幅も広く、キャラクターの“人格”を視聴者に強く印象づけるのに適しています。具体的にはドン・キホーテの公式キャラクターである「ドンペン」や「ドンコ」があげられます。YouTubeでは売り場の裏側をキャラクターが紹介するコンテンツや、「ドンペンくんのえかきうた」などのキャラクター独自のコンテンツが展開されており、ユーザーから愛されるキャラクターとなっています。
このように、SNSごとに適した発信スタイルや戦略を取り入れることで、企業公式キャラクターのSNSアカウントは強力なブランディングツールとして機能します。キャラクターが“情報の発信者”として立つことで、企業自体への親近感と信頼が醸成されていくのです。
ここでは、主要なSNSごとに、キャラクター運用がどのように行われているか、実際の事例を交えながら紹介していきます。
X(旧Twitter)
X(旧Twitter)は、リアルタイム性とユーザーとの双方向コミュニケーションが特徴的なSNSです。キャラクターの“中の人”がユーザーと自然に会話を交わすことで、企業のイメージを柔らかく、親しみやすくする効果があります。代表的な事例としてよく挙げられるのが、Pontaの公式アカウントです。Pontaでは公式キャラクターのポンタが週に2回程度、ポンタの日常生活を紹介しており、ポンタのイラストツイートは他のツイートに比べてリポストやリプライも多くなっており、うまくエンゲージメントにつなげている例といえるでしょう。このようにキャラクター性を持たせた投稿スタイルは、ユーザーとの心理的な距離を縮める上で非常に効果的です。
また、株式会社ギンビスでは、代表的な商品であるたべっ子どうぶつの着ぐるみを使った写真を投稿しています。
企業の雰囲気を伝えつつ、ユーザーの関心を引くきっかけとなるため、採用活動やブランディングとの親和性が高いのが特徴です。真面目な印象の中にもキャラクターによる温かみを感じさせる投稿が、好感を持たれる傾向にあります。
TikTok
TikTokは、短尺動画でインパクトを残すことが求められるSNSであり、キャラクターが持つ動きや声、テンポ感を活かしたコンテンツ制作に向いています。たとえば、自治体のキャラクターが地域紹介を行う動画や、企業のマスコットが人気の音楽に合わせてダンスする動画などが高い視聴数を獲得しています。TikTokのユーザーは若年層が多く、エンタメ要素の強い投稿が受け入れられやすいため、キャラクターの“遊び心”を活かした戦略が求められます。人間味とバーチャル感のバランスを保ちながら、企業の認知を高められることが大きな強みです。
YouTube
YouTubeでは、動画によってキャラクターのストーリーや世界観を長時間にわたって伝えることができるため、より深いファン層の獲得に繋がります。特に、Vtuber形式でキャラクターが配信するスタイルは、近年多くの企業で取り入れられており、商品紹介や質問コーナー、雑談動画など、さまざまな内容で活用されています。実写とアニメーションのハイブリッド構成や、ナレーション付きのミニドラマ仕立てなど、表現の幅も広く、キャラクターの“人格”を視聴者に強く印象づけるのに適しています。具体的にはドン・キホーテの公式キャラクターである「ドンペン」や「ドンコ」があげられます。YouTubeでは売り場の裏側をキャラクターが紹介するコンテンツや、「ドンペンくんのえかきうた」などのキャラクター独自のコンテンツが展開されており、ユーザーから愛されるキャラクターとなっています。
このように、SNSごとに適した発信スタイルや戦略を取り入れることで、企業公式キャラクターのSNSアカウントは強力なブランディングツールとして機能します。キャラクターが“情報の発信者”として立つことで、企業自体への親近感と信頼が醸成されていくのです。
企業公式キャラクターSNSアカウントの関連職種
企業公式キャラクターのSNS運用に関わる職種には、以下のようなものがあります。
● SNSマーケター
● キャラクタープランナー
● グラフィックデザイナー
● 映像クリエイター
● コミュニティマネージャー
中心となるのは、SNSの戦略を立て投稿を管理するSNSマーケターです。彼らは投稿計画やKPIの設計、数値分析などを担い、運用全体の方針を決定します。また、キャラクターの個性やトーンを維持するためには、キャラクタープランナーの存在が欠かせません。さらに、投稿画像や動画の制作を行うグラフィックデザイナーや映像クリエイター、ユーザーとのやり取りを担当するコミュニティマネージャーなど、多様な職種が連携して1つのアカウントを作り上げていきます。
キャラクター制作に関する具体的な実務内容については、こちらの記事もぜひご覧ください。
≫企業キャラクターとは?人気・有名な成功例・作り方・デザインなど
● SNSマーケター
● キャラクタープランナー
● グラフィックデザイナー
● 映像クリエイター
● コミュニティマネージャー
中心となるのは、SNSの戦略を立て投稿を管理するSNSマーケターです。彼らは投稿計画やKPIの設計、数値分析などを担い、運用全体の方針を決定します。また、キャラクターの個性やトーンを維持するためには、キャラクタープランナーの存在が欠かせません。さらに、投稿画像や動画の制作を行うグラフィックデザイナーや映像クリエイター、ユーザーとのやり取りを担当するコミュニティマネージャーなど、多様な職種が連携して1つのアカウントを作り上げていきます。
キャラクター制作に関する具体的な実務内容については、こちらの記事もぜひご覧ください。
≫企業キャラクターとは?人気・有名な成功例・作り方・デザインなど
企業公式キャラクターはSNSを活用して愛されるキャラに育てる
本記事では、企業公式キャラクターのSNS活用について、その概要やメリット・デメリット、具体的なSNS活用の事例などについて詳しく解説しました。企業公式キャラクターのSNSアカウントは、単なる広報手段にとどまらず、ユーザーとの信頼関係を築き、企業の“顔”として存在感を発揮する貴重な資産です。運用には戦略性や表現力、継続的な工夫が求められますが、その分、企業のブランディングに直接結びつく大きな成果を得ることができます。
自分がかかわったキャラクターがユーザーから愛され、企業を代表するキャラクターとなることは、大きなやりがいを得られるはずです。キャラクターSNS運用に関わる仕事に興味のある方は、求人情報ページをぜひチェックしてみてください。
日本唯一のキャラクター業界限定の求人サイト「キャラ転」ではキャラクターやSNS運用に関する求人を数多く掲載していますので、ぜひお気軽にご覧ください。
自分がかかわったキャラクターがユーザーから愛され、企業を代表するキャラクターとなることは、大きなやりがいを得られるはずです。キャラクターSNS運用に関わる仕事に興味のある方は、求人情報ページをぜひチェックしてみてください。
日本唯一のキャラクター業界限定の求人サイト「キャラ転」ではキャラクターやSNS運用に関する求人を数多く掲載していますので、ぜひお気軽にご覧ください。
新着の記事
- 3DCGデザイナーのポートフォリオ作成のコツや注意点について
- キャラクターデザイナーに求められるスキルとは?実務で評価される能力を解説
- キャラクターイラストの描き方ガイド|初心者が上達するためのコツ
- 声優が実践したい喉のケア方法!おすすめの習慣やNG行動とは
- 声優は独学でなれる?独学で身につく力・練習法・スクールとの違いは
- コンポジターとは?仕事内容・平均年収とキャリアの始め方を紹介
- ゲームイラストレーターになるには?必要スキル・未経験からの目指し方
- モーションキャプチャーソフトとは?種類や選び方、おすすめの製品について
- キャラクターの性格の作り方とは?魅力を引き出す設定方法を解説
- 造形師と原型師の違いは?仕事内容や求められるスキルを徹底比較